
 |
|
|
|
<はじめに> |
 |
| 例えば、葛根湯という漢方は次の七つの生薬から成り立っています。 葛根(かっこん)--くずの根 4.0 大棗(たいそう)--ナツメの果実 3.0 麻黄(まおう)--マオウの茎 3.0 甘草(カンゾウ)2.0 桂皮(けいひ)--ケイ樹の幹皮 2.0 芍薬(しゃくやく)--シャクヤクの根 2.0 生姜(しょうきょう)--ショウガ 1.0 |
 |
|||
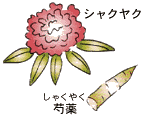 |
 |
 |
||
| この七味の薬草の服用法について「水400を以て葛根・麻黄を煮て80を減じ白沫を去り他の諸薬を加えて 再び 煮て120に煮つめ滓を去り三回に分服」と古書に記載されています。 煎剤とか湯剤といわれているのはこのよう な手法で服用するからです。 |
| さて、昭和42年、漢方薬が医療用漢方製剤として医療保険適用となり、 病・医院で用いられるようになりました。 それ以前は漢方医学(東洋医学)を勉強し研究した一部の医師、 薬剤師が自費投薬あるいは販売の方法にて医療に供していたわけです。 いわゆる保険適用のない姿で市販されていたのです。 医療制度の変化により漢方薬も医師の診察によって、 医療機関で投薬されたり、処方箋によって市中の薬局にて調剤され、 入手できるようになりました。 処方される漢方薬の大部分は、エキス製剤で煎剤・湯剤は少ないようです。 また、このエキス製剤は煎じる手間が省けて携帯にとても便利です。 漢方は万能ではありません。 これは近代医学にも同じことがいえることですが、 生薬を用いて病気とたたかってきた長い時代の経験を大切に して 漢方への理解を深めたいものです。 |
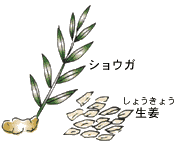 |
||
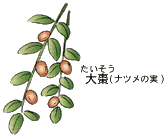 |
|||
| <漢方とは> 漢方という言葉は江戸時代に入ってきたオランダ医学(蘭学)に対して、漢の国、 すなわち中国の伝統的医学に基づいた医学大系を表現する言葉として理解されています。 中国では漢方とは言いません。 漢方という言葉は日本的な解釈の上に成り立った言葉で、 中国では伝統医学や、西医(西洋医学)に対して中医という呼び方をします。 |
|
<漢方薬と民間薬>
|
| <漢方と西洋薬> 漢方薬は天然の生薬を使っています。 一つの漢方(処方)は、数種類の生薬で構成されています。 そのため、多くの成分が含まれていて、 生薬の働きの強弱と組み合わせによって、さまざまな効果が期待されます。 西洋薬は作用の強い単一成分を発見しその中から 一つの活性成分を抽出して化学構造を決定し合成されます。 このような化学的手法で薬となるのです。 |
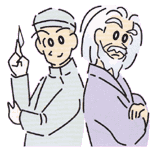 |
| <漢方と西洋医学> 西洋医学と比較すると漢方には、さまざまな至らぬ点もあります。 病気の診断法一つを見ても、今日の西洋医学の極めて科学的な診断の方法とは到底太刀打ちできません。 又、病原を極め、病巣をつく点でも、西洋医学は高度な技術を見せているし、外科的手術においてもそうです。 しかし、西洋医学は局所の病気に対しての治療法は発達しているけれども、 体全体から病気を見る点では不十分なこともあります。 また慢性病とか、原因のはっきりつかめない病気に対しても力が弱いこともあります。 この点で体全体から病気を考えるという 漢方の良さを否定することは出来ません。 |
| /長崎県薬局マップ/OTCについて/トピックス/ /Q&A /服薬情報(英語)/行政/リンク集 /  |
| Copyright(C),1998,社団法人 長崎県薬剤師会 |